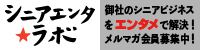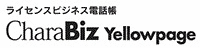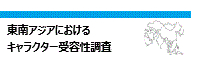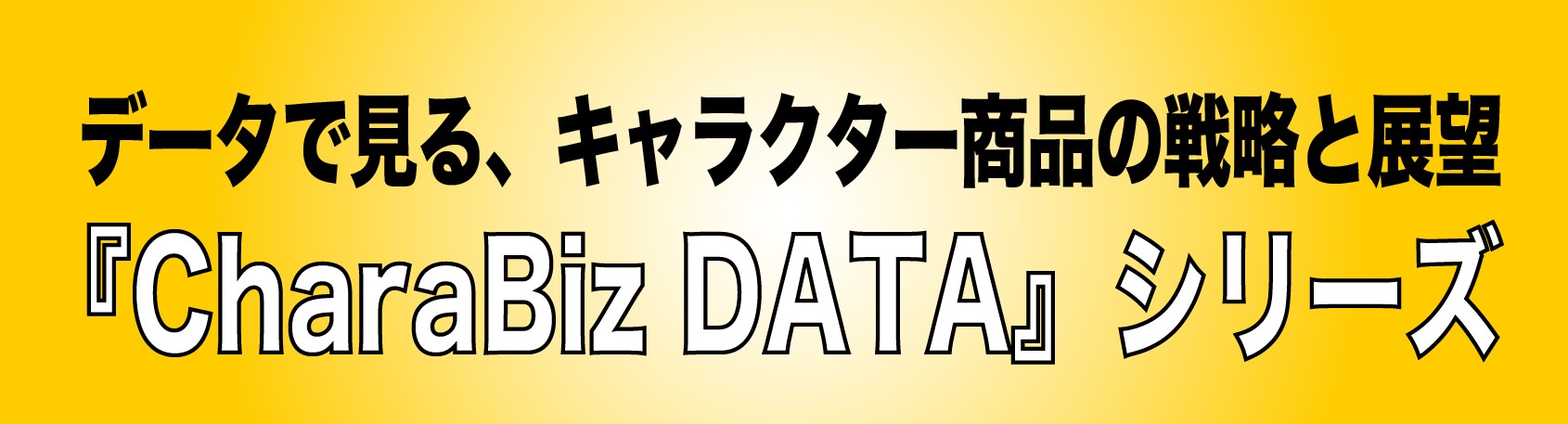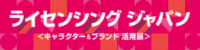子どものマーケティングや子どもコンテンツビジネスに関する基礎知識を学ぶ
第5期 子どもコンテンツフォーラム(CCF)
子どもコンテンツビジネス講座【基礎編】/【実践ビジネス編】
第5期 子どもコンテンツフォーラム(CCF)
子どもコンテンツビジネス講座【基礎編】/【実践ビジネス編】
プログラムの紹介
第1回
7月23日(火)
キックオフセミナー「いま改めて子ども向けメディアコンテンツについて考える」
16:00~18:00
子どもへのスマートフォンやタブレットの普及、コロナ禍での深夜アニメ視聴、ソーシャルメディアやソーシャルゲームの使用拡大など、メディアにおけるさまざまな問題が懸念される一方で、アニメやインターネットが、子どもたちの学びや遊び、コミュニケーションなどを大きく変え、また、日常にストレスを感じている子どもたちにとっての居場所になっているという話も聞きます。今回のシンポジウムは、子どものメディアコンテンツについて、最近の動向や課題もふまえながら子どもにとってのポジティブなメディアコンテンツの効果と活用について考えていきます。
(1)<基調講演>子どもとメディア、メディア・リテラシー
講師:登丸あすか氏(文京学院大学 人間学部コミュニケーション社会学科 准教授)
スマートフォンやタブレットなど新しいメディアの登場によって子どものメディア環境は大きく変化しました。そうした変化を踏まえて、現在のメディア社会に必要なメディア・リテラシーの考え方を紹介します。
(2)キックオフセッション
登壇者:登丸あすか氏(文京学院大学 人間学部コミュニケーション社会学科 准教授)
土本 幹郎氏 (株式会社 Kumarba 「クマーバチャンネル」プロジェクトリーダー)
亀山 泰夫氏 (慶應義塾大学メディアデザイン研究所研究員/
一般社団法人CiP協議会事務局 シニアディレクター)
基調講演、および最近の家族の生活環境や子どもを取り巻くメディア環境の変化などの話題も交えながら、子ども向けメディアコンテンツの影響、効果と今後の方向性や課題について考えてみたいと思います。

登丸あすか(とまる あすか)氏
文京学院大学 人間学部コミュニケーション社会学科 准教授
立命館大学大学院社会学研究科在籍時よりでメディア・リテラシーの研究を始める。現在、文京学院大学でメディアについて教えながら、市民講座などで「子どもとメディア」「ジェンダーとメディア」などをテーマとした講師も務める。
文京学院大学 人間学部コミュニケーション社会学科 准教授
立命館大学大学院社会学研究科在籍時よりでメディア・リテラシーの研究を始める。現在、文京学院大学でメディアについて教えながら、市民講座などで「子どもとメディア」「ジェンダーとメディア」などをテーマとした講師も務める。

土本 幹郎(つちもと みきろう)氏
株式会社 Kumarba「クマーバチャンネル」プロジェクトリーダー
前職の通信教育企業では、出産育児メディアや、通信教材のキャラクターライセンス・企業アライアンスを担当。2021年から株式会社Kumarbaに参画。登録者数50万人を超えるキッズ向けYouTubeチャンネル「クマーバチャンネル」ではプロジェクトリーダーとして、チャンネル全体の方針の決定から、マーケティング・プロモーション・ライセンス・企業コラボまで幅広く担う。テレビアニメ「クマーバ」においては、宣伝プロデューサーとしてプロモーション計画の設計から、他社コラボの折衝を担当。
株式会社 Kumarba「クマーバチャンネル」プロジェクトリーダー
前職の通信教育企業では、出産育児メディアや、通信教材のキャラクターライセンス・企業アライアンスを担当。2021年から株式会社Kumarbaに参画。登録者数50万人を超えるキッズ向けYouTubeチャンネル「クマーバチャンネル」ではプロジェクトリーダーとして、チャンネル全体の方針の決定から、マーケティング・プロモーション・ライセンス・企業コラボまで幅広く担う。テレビアニメ「クマーバ」においては、宣伝プロデューサーとしてプロモーション計画の設計から、他社コラボの折衝を担当。
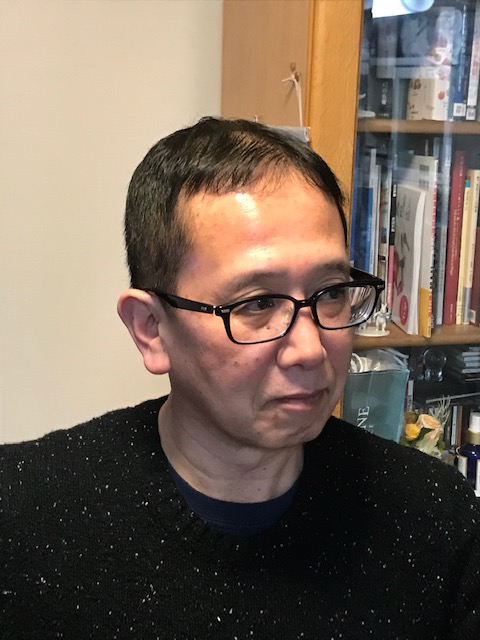
亀山 泰夫(かめやま やすお)氏
慶應義塾大学メディアデザイン研究所研究員
一般社団法人CiP協議会事務局 シニアディレクター
(世界オタク研究所主席研究員、CiPプロデューサー)
2012年まで、広告代理店、プロデュース会社で、アニメをはじめとするテレビ番組や、美術展、出版物等の企画プロデューサーとして活動。
2013年以後、フリーとしてアニメの周辺事業に関わりつつ、ポップカルチャー研究を開始し、2020年に慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科にて博士
(メディアデザイン学)の学位を取得。
現在は、CiP協議会が進めるオタク文化研究機関構築プロジェクト「世界オタク研究所」の主席研究員としてアニメを中心としたポップカルチャー研究を進めるとともに、同協議会が港区竹芝地区に開設した拠点スペース「CiP」のプロデューサーとして活動中。
慶應義塾大学メディアデザイン研究所研究員
一般社団法人CiP協議会事務局 シニアディレクター
(世界オタク研究所主席研究員、CiPプロデューサー)
2012年まで、広告代理店、プロデュース会社で、アニメをはじめとするテレビ番組や、美術展、出版物等の企画プロデューサーとして活動。
2013年以後、フリーとしてアニメの周辺事業に関わりつつ、ポップカルチャー研究を開始し、2020年に慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科にて博士
(メディアデザイン学)の学位を取得。
現在は、CiP協議会が進めるオタク文化研究機関構築プロジェクト「世界オタク研究所」の主席研究員としてアニメを中心としたポップカルチャー研究を進めるとともに、同協議会が港区竹芝地区に開設した拠点スペース「CiP」のプロデューサーとして活動中。
第2回
8月27日(火)
基礎編「子どもの発達とメディアについて」
16:00~17:30
メディアコンテンツのエイジレス化、フラット化が進むなかで、まずは発達や行政における子どもの定義と、子どもの年齢発達と遊びや教育、それらの最近のトレンドなどについて触れた上で、子どもの発達とメディア(コンテンツ)接触について、最近のデジタル生活のなかでの変化や留意点ならびに今後の課題などについて専門講師よりお話いただきます。
子どもの発達とメディア(仮)
講師:七海 陽氏(相模女子大学 学芸学部 子ども教育学科 准教授)
子どもの発達とメディア(コンテンツ)接触について、最近のデジタル生活の中での変化や留意点ならびに今後の課題などを考察します
【データと基礎知識】
・子どもとは?
・子どもの年齢発達と遊び・教育
・最近の子どもの特徴
【課題】子どもの発達とメディア、コンテンツにおける役割・留意点
子どもの発達とメディア(仮)
講師:七海 陽氏(相模女子大学 学芸学部 子ども教育学科 准教授)
子どもの発達とメディア(コンテンツ)接触について、最近のデジタル生活の中での変化や留意点ならびに今後の課題などを考察します
【データと基礎知識】
・子どもとは?
・子どもの年齢発達と遊び・教育
・最近の子どもの特徴
【課題】子どもの発達とメディア、コンテンツにおける役割・留意点

七海 陽(ななみ よう)氏
相模女子大学 学芸学部 子ども教育学科 准教授
専門は児童文化学。幼児・児童期の発達とICT・デジタルメディア など。1990年白百合女子大学文学部児童文化学科卒業後、富士通株式会社入社。情報・メディア産業向け営業、2000年BSデジタルデータ放送会社設立に従事し2002年同社を退職。「佐藤家のデジタル生活 子どもたちはどうなるの?」(草土文化)を上梓し、フリーランスで執筆、講演を行う。白百合女子大学児童文化研究センター、お茶の水女子大学文教育学部心理学講座の研究員ならびに複数の大学で非常勤講師を務める。2005年浜松大学こども健康学科専任講師を経て、2009年相模女子大学子ども教育学科専任講師。2014年より現職
相模女子大学 学芸学部 子ども教育学科 准教授
専門は児童文化学。幼児・児童期の発達とICT・デジタルメディア など。1990年白百合女子大学文学部児童文化学科卒業後、富士通株式会社入社。情報・メディア産業向け営業、2000年BSデジタルデータ放送会社設立に従事し2002年同社を退職。「佐藤家のデジタル生活 子どもたちはどうなるの?」(草土文化)を上梓し、フリーランスで執筆、講演を行う。白百合女子大学児童文化研究センター、お茶の水女子大学文教育学部心理学講座の研究員ならびに複数の大学で非常勤講師を務める。2005年浜松大学こども健康学科専任講師を経て、2009年相模女子大学子ども教育学科専任講師。2014年より現職
第3回
9月3日(火)
基礎編「子どものマーケティングについて」
16:00~17:30
子どものマーケティングについて、一般的な(大人向け)マーケティングとの違い、特にターゲットとしての子どもの特徴について整理した上で、専門講師より、海外での子どもマーケティングの流れなどもふまえて、子どもマーケティング及び子どもコンテンツマーケティングの今後の方向性や留意点についてお話いただきます。
子ども向けマーケティングの留意点と今後の方向性
講師:天野恵美子氏(関東学院大学 経営学部 教授)
・子どものマーケティングとは?
・子どもの消費活動の領域
・子どもマーケティングのターゲットの特徴
【課題】子どもマーケティングにおける留意点と今後の方向
子ども向けマーケティングの留意点と今後の方向性
講師:天野恵美子氏(関東学院大学 経営学部 教授)
デジタル化、少子化、高齢化が進展する中、子どもの消費や子どもを取り巻くマーケティングには大きな変化が生じています。「成長途上の消費者」としての子どもをターゲットにしたマーケティングにおける留意点と今後の方向性について考えます。
【データと基礎知識】・子どものマーケティングとは?
・子どもの消費活動の領域
・子どもマーケティングのターゲットの特徴
【課題】子どもマーケティングにおける留意点と今後の方向

天野恵美子(あまの えみこ)氏
関東学院大学 経営学部 教授
1974年神奈川県生まれ。専門はマーケティング、消費者問題。秋田大学教育文化学部を経て、現職。子どもや若者の消費やマーケティングに関する調査・研究を行う。主な著書に『子ども消費者へのマーケティング戦略―熾烈化する子どもビジネスにおける自制と規制―』(単著、2017年、ミネルヴァ書房)、『新しい消費者教育: これからの消費生活を考える』(共著、2019年、慶應義塾大学出版会)他がある。
関東学院大学 経営学部 教授
1974年神奈川県生まれ。専門はマーケティング、消費者問題。秋田大学教育文化学部を経て、現職。子どもや若者の消費やマーケティングに関する調査・研究を行う。主な著書に『子ども消費者へのマーケティング戦略―熾烈化する子どもビジネスにおける自制と規制―』(単著、2017年、ミネルヴァ書房)、『新しい消費者教育: これからの消費生活を考える』(共著、2019年、慶應義塾大学出版会)他がある。
第4回
9月10日(火)
基礎編「子どもコンテンツの心理効果について」
16:00~17:30
最近のデータから子どもの年齢ごとのコンテンツ嗜好や効果についてのデータをご紹介し、子どもの発達と物語やキャラクターの役割について触れた後に、専門講師より、アニメなどの事例を中心に子どもコンテンツのポジティブな心理的機能・効果についてお話します。
現代メディアと心理学~アニメ、ゲームと人のこころ~
講師:薮田 拓哉氏(甲子園大学 心理学部 助教授)
本講座では、メディアや子どもに関する心理学の基礎知識と、アニメやゲームなど幅広い世代に享受されているコンテンツの心理学研究や臨床現場での実践的な取り組みを紹介しながら、子どもコンテンツの心理的効果について検討していきます
【データと基礎知識】
・子どもコンテンツのカテゴリー
・子どものコンテンツ嗜好
・子どもと物語
・子どもとキャラクター
【課題】子どもコンテンツの心理効果について
現代メディアと心理学~アニメ、ゲームと人のこころ~
講師:薮田 拓哉氏(甲子園大学 心理学部 助教授)
本講座では、メディアや子どもに関する心理学の基礎知識と、アニメやゲームなど幅広い世代に享受されているコンテンツの心理学研究や臨床現場での実践的な取り組みを紹介しながら、子どもコンテンツの心理的効果について検討していきます
【データと基礎知識】
・子どもコンテンツのカテゴリー
・子どものコンテンツ嗜好
・子どもと物語
・子どもとキャラクター
【課題】子どもコンテンツの心理効果について
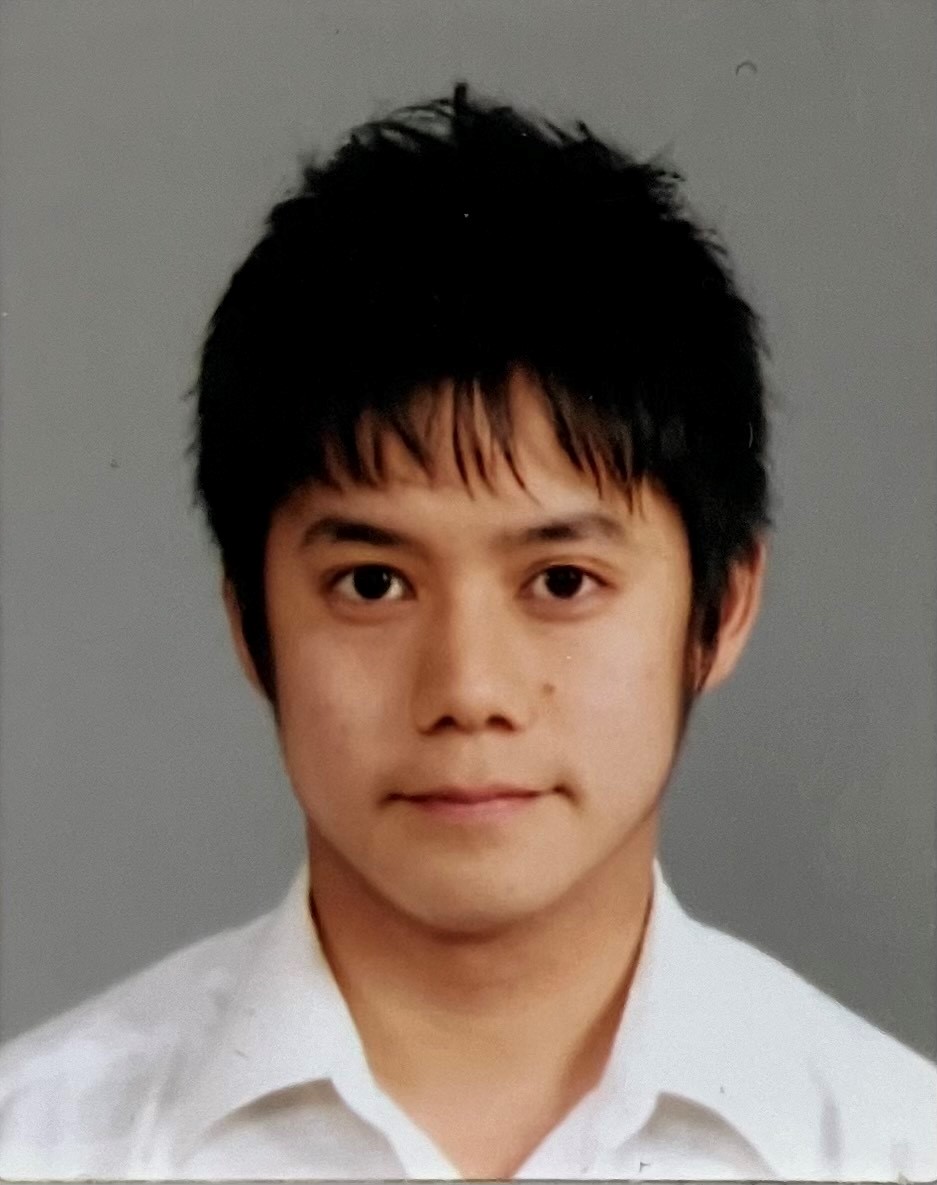
薮田 拓哉(やぶた たくや)氏
甲子園大学 心理学部 助教
和歌山県出身。智辯学園和歌山高校卒業後、同志社大学心理学部、大阪大学大学院人間科学研究科にて心理学を学ぶ。2020年より大阪教育大、佛教大、関西医療大などの大学や専門学校にて非常勤講師を務め、2023年に大阪大学大学院人間科学研究科教育支援デジタルクローン共同研究講座特任助教(常勤)に着任。2024年より現職(甲子園大学心理学部助教)。専門は臨床心理学、アニメの心理学。現在は大学生を対象にアニメ視聴が心の癒しをもたらすメカニズムについて臨床心理学やポジティブメディア心理学の視点から研究している。また、臨床心理士、公認心理師として主に発達特性や学校不適応によって悩みを抱える子どもやその家族支援に携わっている。趣味は高校野球観戦、アニメ鑑賞、旅などその他多数。
甲子園大学 心理学部 助教
和歌山県出身。智辯学園和歌山高校卒業後、同志社大学心理学部、大阪大学大学院人間科学研究科にて心理学を学ぶ。2020年より大阪教育大、佛教大、関西医療大などの大学や専門学校にて非常勤講師を務め、2023年に大阪大学大学院人間科学研究科教育支援デジタルクローン共同研究講座特任助教(常勤)に着任。2024年より現職(甲子園大学心理学部助教)。専門は臨床心理学、アニメの心理学。現在は大学生を対象にアニメ視聴が心の癒しをもたらすメカニズムについて臨床心理学やポジティブメディア心理学の視点から研究している。また、臨床心理士、公認心理師として主に発達特性や学校不適応によって悩みを抱える子どもやその家族支援に携わっている。趣味は高校野球観戦、アニメ鑑賞、旅などその他多数。
第5回
9月17日(火)
基礎編「子どもコンテンツトレンドについて」
16:00~17:30
広義の子どもコンテンツについてのカテゴライズと、各カテゴリーについての現状をデータや年表などで整理しながら、専門講師より子どもコンテンツのトレンドと進化の流れ、最近の動向や課題などについてお話いただきます。
子ども向けコンテンツのトレンドと進化(仮)
講師:中村 仁氏(跡見学園女子大学観光コミュニティ学部観光デザイン学科 准教授)
子ども向けコンテンツとそれを取り巻くさまざまなモノ・サービスについての現状を歴史的な視点も踏まえながらトレンドや進化の流れについてお話します。子どもたちはテレビでの番組視聴やタブレット等での動画配信でコンテンツに触れるだけではなく、ショッピングモールなどでの着ぐるみショー、飲食店のコラボメニュー、さらには遊園地等での仮装など画面からリアルへのつながりを整理します。
【データと基礎知識】
・テレビ:子供番組、幼児教育番組、アニメ番組の現状
・絵本・児童書・マンガ
・子どもとインターネット
・子ども空間
・イベント・ワークショップ
【課題】子どもコンテンツの進化と子どもにおける課題
子ども向けコンテンツのトレンドと進化(仮)
講師:中村 仁氏(跡見学園女子大学観光コミュニティ学部観光デザイン学科 准教授)
子ども向けコンテンツとそれを取り巻くさまざまなモノ・サービスについての現状を歴史的な視点も踏まえながらトレンドや進化の流れについてお話します。子どもたちはテレビでの番組視聴やタブレット等での動画配信でコンテンツに触れるだけではなく、ショッピングモールなどでの着ぐるみショー、飲食店のコラボメニュー、さらには遊園地等での仮装など画面からリアルへのつながりを整理します。
【データと基礎知識】
・テレビ:子供番組、幼児教育番組、アニメ番組の現状
・絵本・児童書・マンガ
・子どもとインターネット
・子ども空間
・イベント・ワークショップ
【課題】子どもコンテンツの進化と子どもにおける課題

中村 仁(なかむら じん)氏
跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部 観光デザイン学科 准教授
1976年、東京都生まれ。宇都宮大学農学部農業経済学科卒業、京都大学大学院法学研究科政治学専攻修士課程修了後、東京工業大学より論文により博士(学術)を取得。国際連合世界食糧計画、帝国石油株式会社を経て研究活動の道に進む。産能短期大学専任講師、東京大学大学院情報学環特任講師、日本経済大学大学院経営学研究科准教授兼クリエイティブ産業研究所長を経て現職。(跡見学園女子大学教授)。社会・経済システム学会理事、日本テレワーク学会理事、一般社団法人大都市政策研究機構監事の他、日本外国特派員協会会員として東洋経済オンラインなどでの執筆活動を行なっている。
社会情報学をベースとして、コンテンツや観光など機能的価値より情緒的価値を基盤とする産業を研究対象としている。主な著書に「クリエイティブ産業論:ファッション・コンテンツ産業の日本型モデル」などがある。近年はアニメツーリズム白書2020にて解説を執筆した。
跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部 観光デザイン学科 准教授
1976年、東京都生まれ。宇都宮大学農学部農業経済学科卒業、京都大学大学院法学研究科政治学専攻修士課程修了後、東京工業大学より論文により博士(学術)を取得。国際連合世界食糧計画、帝国石油株式会社を経て研究活動の道に進む。産能短期大学専任講師、東京大学大学院情報学環特任講師、日本経済大学大学院経営学研究科准教授兼クリエイティブ産業研究所長を経て現職。(跡見学園女子大学教授)。社会・経済システム学会理事、日本テレワーク学会理事、一般社団法人大都市政策研究機構監事の他、日本外国特派員協会会員として東洋経済オンラインなどでの執筆活動を行なっている。
社会情報学をベースとして、コンテンツや観光など機能的価値より情緒的価値を基盤とする産業を研究対象としている。主な著書に「クリエイティブ産業論:ファッション・コンテンツ産業の日本型モデル」などがある。近年はアニメツーリズム白書2020にて解説を執筆した。
第6回
9月24日(火)
基礎編「子どもコンテンツビジネスについて」
16:00~17:30
子どもコンテンツビジネスの市場規模やカテゴリーごとのステークホルダーなどの基礎知識について整理しながら、専門講師を中心に、子どもコンテンツビジネスのビジネススキームや今後の方向性、課題などについてお話いただきます。
子ども向けコンテンツビジネスの構造と現在
講師:亀山 泰夫氏(慶應義塾大学メディアデザイン研究所研究員/一般社団法人CiP協議会事務局 シニアディレクター)
・市場規模、市場動向
・ビジネススキームについて
・ステークホルダーについて
・子どもコンテンツのレーティング(ゲーム、映倫、Google など)
【課題】子どもコンテンツビジネスの流れと今後の課題
子ども向けコンテンツビジネスの構造と現在
講師:亀山 泰夫氏(慶應義塾大学メディアデザイン研究所研究員/一般社団法人CiP協議会事務局 シニアディレクター)
アニメや配信といった映像コンテンツを中心とした子ども向けコンテンツビジネスの仕組みとともに、このビジネスの進化の歴史に触れつつ、現在の状況と課題についてお話しいたします。
【データと基礎知識】・市場規模、市場動向
・ビジネススキームについて
・ステークホルダーについて
・子どもコンテンツのレーティング(ゲーム、映倫、Google など)
【課題】子どもコンテンツビジネスの流れと今後の課題
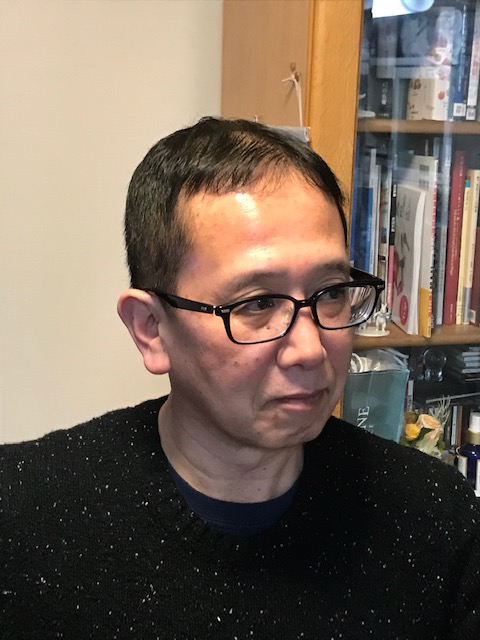
亀山 泰夫(かめやま やすお)氏
慶應義塾大学メディアデザイン研究所研究員
一般社団法人CiP協議会事務局 シニアディレクター
(世界オタク研究所主席研究員、CiPプロデューサー)
2012年まで、広告代理店、プロデュース会社で、アニメをはじめとするテレビ番組や、美術展、出版物等の企画プロデューサーとして活動。
2013年以後、フリーとしてアニメの周辺事業に関わりつつ、ポップカルチャー研究を開始し、2020年に慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科にて博士
(メディアデザイン学)の学位を取得。
現在は、CiP協議会が進めるオタク文化研究機関構築プロジェクト「世界オタク研究所」の主席研究員としてアニメを中心としたポップカルチャー研究を進めるとともに、同協議会が港区竹芝地区に開設した拠点スペース「CiP」のプロデューサーとして活動中。
慶應義塾大学メディアデザイン研究所研究員
一般社団法人CiP協議会事務局 シニアディレクター
(世界オタク研究所主席研究員、CiPプロデューサー)
2012年まで、広告代理店、プロデュース会社で、アニメをはじめとするテレビ番組や、美術展、出版物等の企画プロデューサーとして活動。
2013年以後、フリーとしてアニメの周辺事業に関わりつつ、ポップカルチャー研究を開始し、2020年に慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科にて博士
(メディアデザイン学)の学位を取得。
現在は、CiP協議会が進めるオタク文化研究機関構築プロジェクト「世界オタク研究所」の主席研究員としてアニメを中心としたポップカルチャー研究を進めるとともに、同協議会が港区竹芝地区に開設した拠点スペース「CiP」のプロデューサーとして活動中。
第7回
10月15日(火)
実践ビジネス編「子ども向けメディアコンテンツ開発」
16:00~17:30
アニメ、出版など、最近の子ども向けのメディアコンテンツ嗜好の特徴や開発の事例についてご紹介いただいたあと、企画のポイントや留意点、今後へのヒントなどについてディスカッションします。
【パネラー】
ライター 飯田 一史氏
株式会社ファンワークス 代表取締役 高山 晃氏
【パネラー】
ライター 飯田 一史氏
株式会社ファンワークス 代表取締役 高山 晃氏

飯田 一史(いいだ いっし)氏
ライター
出版社勤務を経てライターに。マーケティング的視点と批評的観点から出版産業やサブカルチャー等について取材&調査して解説する記事を現代ビジネスなどに寄稿している。単著には『いま、子どもの本が売れる理由』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『マンガ雑誌は死んだ』『ウェブ小説の衝撃』『「若者の読書離れ」というウソ-中高生はどのくらい、どんな本を読んでいるのか』などがある。グロービス経営大学院経営学修士(MBA)。
ライター
出版社勤務を経てライターに。マーケティング的視点と批評的観点から出版産業やサブカルチャー等について取材&調査して解説する記事を現代ビジネスなどに寄稿している。単著には『いま、子どもの本が売れる理由』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『マンガ雑誌は死んだ』『ウェブ小説の衝撃』『「若者の読書離れ」というウソ-中高生はどのくらい、どんな本を読んでいるのか』などがある。グロービス経営大学院経営学修士(MBA)。

高山 晃(たかやま あきら)氏
株式会社 ファンワークス 代表取締役
広告代理店、映像制作、アニメプロダクションなどを経て2005年に株式会社ファンワークスを設立。WEBアニメ「やわらか戦車」を皮切りに「がんばれ!ルルロロ」、「英国一家、日本を食べる」などのTVアニメシリーズ。映画、広告、日本地域の観光(クールジャパン)系アニメなどのプロデュースに関わる。2018年4月よりがNetflixオリジナルにて世界190カ国で配信がスタートした「アグレッシブ烈子」が海外で話題となり、2019年セカンドシーズンが決定。中国の最大手IT企業テンセントの人気WEB漫画のアニメ化「兄に付ける薬はない!2」が7月より中国、日本でスタート。8月、アニメ「ざんねんないきもの事典」(NHK Eテレ)の制作&プロデュース。現在も多岐に渡るプロジェクトを推進中。
株式会社 ファンワークス 代表取締役
広告代理店、映像制作、アニメプロダクションなどを経て2005年に株式会社ファンワークスを設立。WEBアニメ「やわらか戦車」を皮切りに「がんばれ!ルルロロ」、「英国一家、日本を食べる」などのTVアニメシリーズ。映画、広告、日本地域の観光(クールジャパン)系アニメなどのプロデュースに関わる。2018年4月よりがNetflixオリジナルにて世界190カ国で配信がスタートした「アグレッシブ烈子」が海外で話題となり、2019年セカンドシーズンが決定。中国の最大手IT企業テンセントの人気WEB漫画のアニメ化「兄に付ける薬はない!2」が7月より中国、日本でスタート。8月、アニメ「ざんねんないきもの事典」(NHK Eテレ)の制作&プロデュース。現在も多岐に渡るプロジェクトを推進中。
第8回
11月19日(火)
実践ビジネス編「子ども商品のブランドコンテンツ開発」
玩具、ゲーム、キャラクターといったいわゆるコンテンツ商品だけでなく、衣食まわりなどさまざまな商品が持つ子ども要素やブランドシンボルなどをいかにコンテンツ化し、新しい付加価値として開発するか、最近の事例をご紹介いただきながら、開発のヒントや留意点(デザイン、安全性、操作性、子どもにとってのおもしろさ)などについてディスカッションします。
【パネラー】
株式会社ナルミヤ・インターナショナル 代表取締役執行役員社長 國京 紘宇氏
株式会社ロッテ マーケティング本部 ブランド戦略部 焼き菓子企画課 課長 本原 正明氏
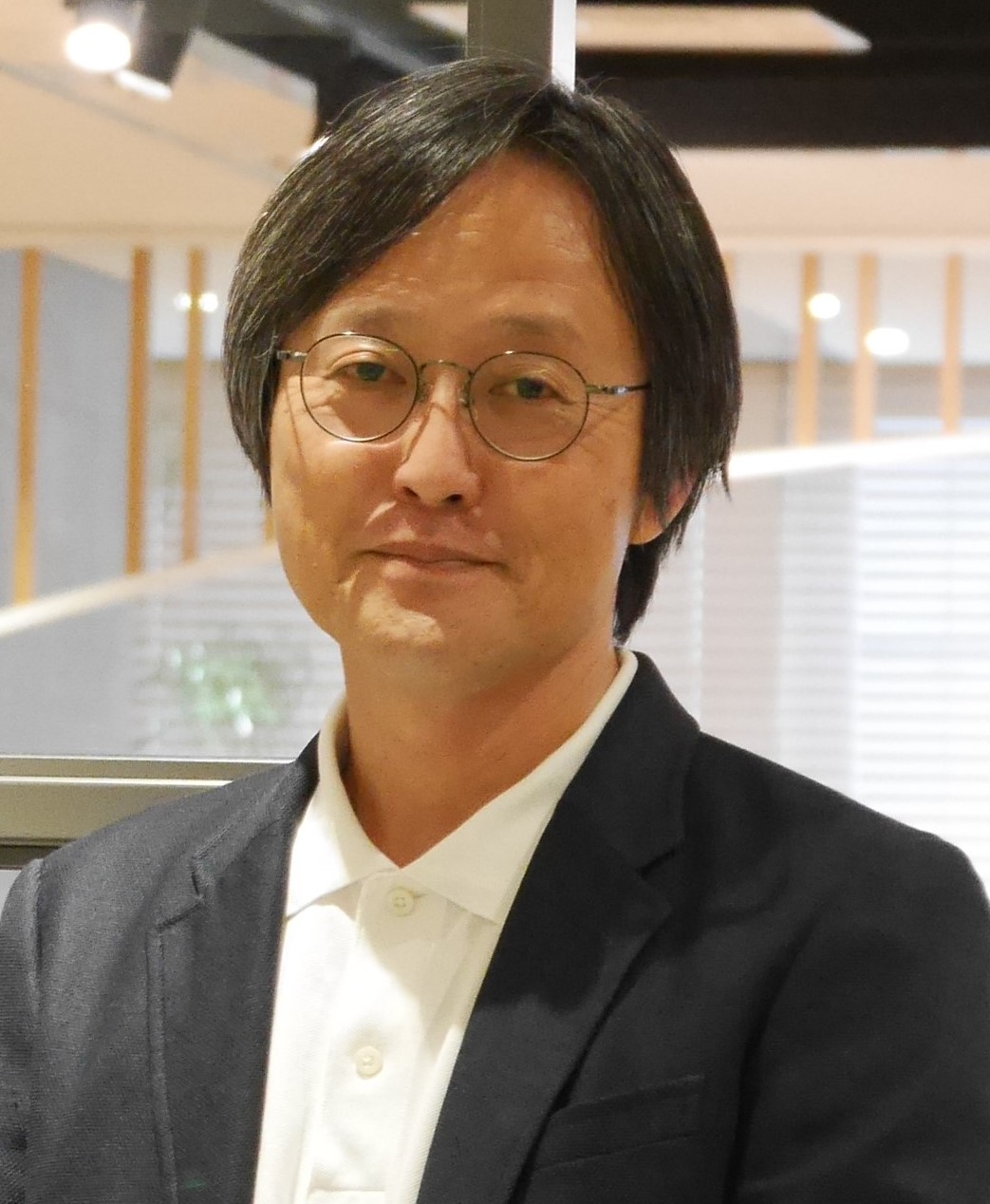
國京 紘宇(くにきょう ひろたか)氏
株式会社ナルミヤ・インターナショナル 代表取締役執行役員社長
2001年トーマツコンサルティング(現デロイトトーマツコンサルティング)入社、03年ユージン(現タカラトミーアーツ)入社、07年同社常務執行役員、11年フィールズ(現円谷フィールズホールディングス)入社、17年ナルミヤ・インターナショナル執行役員経営企画室長、18年常務執行役員経営企画室長、20年ラブスト取締役(現任)、23年5月から現職。
株式会社ナルミヤ・インターナショナル 代表取締役執行役員社長
2001年トーマツコンサルティング(現デロイトトーマツコンサルティング)入社、03年ユージン(現タカラトミーアーツ)入社、07年同社常務執行役員、11年フィールズ(現円谷フィールズホールディングス)入社、17年ナルミヤ・インターナショナル執行役員経営企画室長、18年常務執行役員経営企画室長、20年ラブスト取締役(現任)、23年5月から現職。

本原 正明(ほんばら まさあき)氏
株式会社ロッテ マーケティング本部 ブランド戦略部 焼き菓子企画課 課長
2007年株式会社ロッテに入社。同年、ロッテ商事株式会社に配属となり、菓子営業(近畿)および本社営業企画部を経て、2010年より商品開発部に所属(現・マーケティング本部)。2016年よりチョコパイブランドを担当し、現在はビスケット事業の責任者とコアラのマーチやトッポ、パイの実、子供菓子(ビックリマン含むキャラクター菓子全般も含む)チームの責任者である。ビックリマンブランドはマネジメント立場になっても実務として10年以上担当。課題であったビックリマンファンの裾野を拡大する為に「ワンピース」や「ドラゴンボール」「パズドラ」「スター・ウォーズ」等のコラボ商品を手掛けるだけでなく、千葉ロッテマリーンズとの球団コラボ企画やビックリマン原画展企画、日本記念日協会に認定された「4月1日はビックリマンの日」記念日企画等の様々な斬新なアイデアでビックリマン再ブームの兆し作りに尽力。最近では「ビックリメン」などアニメ化まで実現し、幅広くブランド拡大に挑戦し続けている。
株式会社ロッテ マーケティング本部 ブランド戦略部 焼き菓子企画課 課長
2007年株式会社ロッテに入社。同年、ロッテ商事株式会社に配属となり、菓子営業(近畿)および本社営業企画部を経て、2010年より商品開発部に所属(現・マーケティング本部)。2016年よりチョコパイブランドを担当し、現在はビスケット事業の責任者とコアラのマーチやトッポ、パイの実、子供菓子(ビックリマン含むキャラクター菓子全般も含む)チームの責任者である。ビックリマンブランドはマネジメント立場になっても実務として10年以上担当。課題であったビックリマンファンの裾野を拡大する為に「ワンピース」や「ドラゴンボール」「パズドラ」「スター・ウォーズ」等のコラボ商品を手掛けるだけでなく、千葉ロッテマリーンズとの球団コラボ企画やビックリマン原画展企画、日本記念日協会に認定された「4月1日はビックリマンの日」記念日企画等の様々な斬新なアイデアでビックリマン再ブームの兆し作りに尽力。最近では「ビックリメン」などアニメ化まで実現し、幅広くブランド拡大に挑戦し続けている。
第9回
12月17日(火)
実践ビジネス編「最終回・ワークショップ」
参加者に予めアンケート形式の課題を配布し、記入してもらったシートをコーディネーターの方でまとめていくつかのテーマに整理した上で、ディスカッション形式でまとめます。
【コーディネーター】
子どもコンテンツリサーチ研究所所長/ミッドポイントワークラボ 代表 西岡 直実氏
【コーディネーター】
子どもコンテンツリサーチ研究所所長/ミッドポイントワークラボ 代表 西岡 直実氏

西岡 直実(にしおか なおみ)
子どもコンテンツリサーチ研究所所長/ミッドポイントワークラボ 代表
子どもの遊びや物語、キャラクターの心理効果などの研究をベースに、子ども調査の企画・分析、ワークショップの企画・実施、子どもコンテンツに関する情報サービス・コンサルティングなどを行う。広告会社ADKにて、アニメ番組やキャラクターのマーケティング、子どものリサーチ、教育番組の製作監修、時代予測などの仕事に関わる。2013年に退社し、子どもとコンテンツの研究所ミッドポイント・ワークラボを設立。また、2003年よりキャラクターや物語づくりを行う子どものワークショップを開催している。一橋大学社会学部卒業。放送大学大学院人間発達科学修士課程修了。日本発達心理学会、日本子ども学会、日本社会心理学会、日本アニメーション学会、絵本・児童文学研究センター等の会員。著書(共著)『図解でわかるキャラクターマーケティング』。子どもコンテンツや子ども市場に関する講演や執筆活動なども行う。
子どもコンテンツリサーチ研究所所長/ミッドポイントワークラボ 代表
子どもの遊びや物語、キャラクターの心理効果などの研究をベースに、子ども調査の企画・分析、ワークショップの企画・実施、子どもコンテンツに関する情報サービス・コンサルティングなどを行う。広告会社ADKにて、アニメ番組やキャラクターのマーケティング、子どものリサーチ、教育番組の製作監修、時代予測などの仕事に関わる。2013年に退社し、子どもとコンテンツの研究所ミッドポイント・ワークラボを設立。また、2003年よりキャラクターや物語づくりを行う子どものワークショップを開催している。一橋大学社会学部卒業。放送大学大学院人間発達科学修士課程修了。日本発達心理学会、日本子ども学会、日本社会心理学会、日本アニメーション学会、絵本・児童文学研究センター等の会員。著書(共著)『図解でわかるキャラクターマーケティング』。子どもコンテンツや子ども市場に関する講演や執筆活動なども行う。
第10回
1月21日(火)
コラボ会議(クロージング・シンポジウム)
13:00~17:00
この10年の間に、子どものいる世帯で共働きが7割弱となり、テレワークの普及、育児休暇取得率の上昇、子どもの預かり場所の多様化などにより、家族の休日や子どもの放課後の時間の過ごし方などが大きく変化しています。
また、特にコロナ禍以降、子どもの貧困や小中学生の不登校の急増、体験格差などの社会問題や、長引く物価上昇による生活防衛、テーマパーク入場料などコンテンツの価格自体の変化など、子どもや親子のコンテンツ消費行動にも影響が見られます。
一方で、少子化を背景に、子どものみを対象としたコンテンツは減少し、また、大人の在宅の増加により、大人向けのコンテンツを子どもが共有する機会も増えています。
今年度のコラボ会議では、少子化と共働き時代を前提とした家族や子どもコンテンツの 方向性について考えます。
<クロージング・セッション(コラボ会議)プログラム>
【基調講演1】
Zからα世代への行動変化の流れに見えてきた未来
産業能率大学 経営学部 教授 同 大学院 総合マネジメント研究科 教授
日経広告研究所 客員 小々馬 敦氏
【基調講演2】
「3丁目のガチャガチャ」が世界を救う
一般社団法人日本ガチャガチャ協会 代表理事/株式会社築地ファクトリー代表取締役 小野尾 勝彦氏
【基調講演3】
『クレーンゲーム』はなぜ人気なのか(仮称)
株式会社タイトー 社長室 室長 兼務SPACE INVADERSブランドマネージャー 金山 富幸氏
【パネルディスカッション】
「コンテンツにおける子どもと大人の境界を考える」
跡見学園女子大学観光コミュニティ学部観光デザイン学科 教授 中村 仁氏
一般社団法人日本ガチャガチャ協会 代表理事/株式会社築地ファクトリー代表取締役 小野尾 勝彦氏
株式会社タイトー 社長室 室長 兼務SPACE INVADERSブランドマネージャー 金山 富幸氏
【ネットワーク交流会】
また、特にコロナ禍以降、子どもの貧困や小中学生の不登校の急増、体験格差などの社会問題や、長引く物価上昇による生活防衛、テーマパーク入場料などコンテンツの価格自体の変化など、子どもや親子のコンテンツ消費行動にも影響が見られます。
一方で、少子化を背景に、子どものみを対象としたコンテンツは減少し、また、大人の在宅の増加により、大人向けのコンテンツを子どもが共有する機会も増えています。
今年度のコラボ会議では、少子化と共働き時代を前提とした家族や子どもコンテンツの 方向性について考えます。
<クロージング・セッション(コラボ会議)プログラム>
【基調講演1】
Zからα世代への行動変化の流れに見えてきた未来
産業能率大学 経営学部 教授 同 大学院 総合マネジメント研究科 教授
日経広告研究所 客員 小々馬 敦氏
【基調講演2】
「3丁目のガチャガチャ」が世界を救う
一般社団法人日本ガチャガチャ協会 代表理事/株式会社築地ファクトリー代表取締役 小野尾 勝彦氏
【基調講演3】
『クレーンゲーム』はなぜ人気なのか(仮称)
株式会社タイトー 社長室 室長 兼務SPACE INVADERSブランドマネージャー 金山 富幸氏
【パネルディスカッション】
「コンテンツにおける子どもと大人の境界を考える」
跡見学園女子大学観光コミュニティ学部観光デザイン学科 教授 中村 仁氏
一般社団法人日本ガチャガチャ協会 代表理事/株式会社築地ファクトリー代表取締役 小野尾 勝彦氏
株式会社タイトー 社長室 室長 兼務SPACE INVADERSブランドマネージャー 金山 富幸氏
【ネットワーク交流会】
| お問い合わせ先 |
株式会社キャラクター・データバンク TEL : 03-5776-2061 FAX : 03-5776-2062 E-mail : info@charabiz.com 受付時間 : 10:00~18:00(土日祝日を除く) |
キャラクタービジネスを協力サポート!CharaBiz Membershipサービスはこちら
アジア地域のキャラクター事情を完全網羅!CharaBiz ASIAはこちら
キャラビズ業界の最新情報をメールマガジン「CharaBiz Mail」で毎週水曜にお届けします!(登録無料)